目次

こんにちは。ジョンソンホームズ川田です。
経営者・社長が現場に出ないほうが会社が成長する、という話を聞いたことはあるでしょうか。
売上の伸びが止まり悩んでいるとしたら、それはすでに今までのやり方、経営トップ(社長)自身のあり方では通用しない状態だといえるかもしれません。
伸びが止まる原因はトップにあると私は断言します。
会社を新しい次のステージへ移行しなければ、会社の成長は停止する。
中小企業の経営者の方は、この視点が抜け落ちがちかもしれません。
そのステージチェンジのためには、トップが自分自身の意識を変え、役割(仕事)を変えていく必要があります。
今回は、経営者・社長が現場に出るデメリットや、経営者・社長が現場から離れて会社の成長のためにすべきことなどについてお話ししていきます。
経営者・社長が現場に出たくなる理由
経営者が現場に出たくなる理由には、主に以下の3つがあります。
- 事業や仕事への熱意が大きい
- 完璧主義で社員の仕事ぶりが心配
- 経営より現場のほうが楽しい
まず、純粋に事業や仕事に対する熱意が大きいため、他の人に任せるのではなく、自らの手で事業を進めたくなる方が多いです。
また、完璧主義な経営者は、社員の仕事ぶりが気になり、現場に足を運ぶケースも。
さらに、経営者が現場の業務に魅力を感じ、経営の複雑さに対して現場仕事のほうが楽しく感じることも少なくありません。
経営者が現場から離れるときの不安
一方で、現場に出続ける経営者は、現場を離れることに対してこのような不安を感じることもあります。
- 利益・パフォーマンスが下がる不安
- 尊敬されなくなる不安
- 存在意義を失う不安
- 現場のことが分からなくなる不安
現場に直接関与していることで利益に大きく貢献していると認識している場合、離れることで利益が減少するのではないかと心配になります。
経営者が自分で業務をこなすことでパフォーマンスが高いと感じている場合は、自分がいなくなることで組織のパフォーマンスが低下するのではないかと心配になるケースも。
また、現場を離れたことで社員から尊敬されなくなるのではないかという不安を抱えることもあります。
そして、自分が現場で働くことで存在意義を感じている経営者は、現場から離れることが「自分の存在意義を失う」ことにつながると恐れている傾向もあります。
しかし、経営者として本来求められるのは経営全体を見渡すことと人材育成。
現場での仕事を他の社員に任せることが重要なのです。
現場にいないと重要な情報を見逃してしまうのではないかという不安を抱く方もいらっしゃいますが、信頼できる社員に現場の報告をさせたり、数字をもとに分析したりなどして、現場の状況を把握する方法も存在します。
情報の整理や分析の方法を確立すれば、経営者が現場にいなくても適切な判断ができるでしょう。
ジョンソンホームズの例
住宅会社であるジョンソンホームズはマルチブランド戦略をとり、年間300棟規模で活動しています。
社員数は約380人(2024年4月時点)です。
※リフォーム、インテリアショップ、飲食、フランチャイズのスタッフも含む
私が会社の指揮を任された2001年当時、創業ブランドである北米輸入住宅の受注棟数は20棟台。
低迷期で規模縮小により社員8人の組織でした。
そこから段階的にステージを移してきて、現在に至ります。
一般的に住宅会社の売上別の成長ステージというのは、4段階に分けられているようです。
- [ステージ1]3億円/15〜20棟/社員5〜6名
- [ステージ2]10億円/50〜60棟/社員20〜30名
- [ステージ3]30億円/100〜200棟/社員50〜80名
- [ステージ4]50億円/200〜500棟/社員80〜200名
ステージ1は、経営トップが自分で売っている、よくいわれる"家業"の域だと思います。
現在20棟台で、棟数、売上を伸ばしたいと望む場合、経営トップは何をすれば良いのでしょうか。
私は次のように考えます。
- 自分が売っているなら売ることをやめるべき
- 売っていないなら次は自社に何が必要かを考える
- 部下に仕事を譲っていく
まず、経営者は営業や現場で先頭に立つのではく、トップにしかできない仕事をやるべきでしょう。
そして、地域に愛されるためのブランディングに取り組んでみるなど、自社に何が必要なのか経営者の視点で考えます。
自分だけの価値観にとらわれないで、部下に仕事をどんどん譲っていくことも大切になっていきます。
必要に応じて現場から離れる勇気を持つことが、企業成長につながる重要な一歩なのです。
経営者・社長が現場に出るデメリット
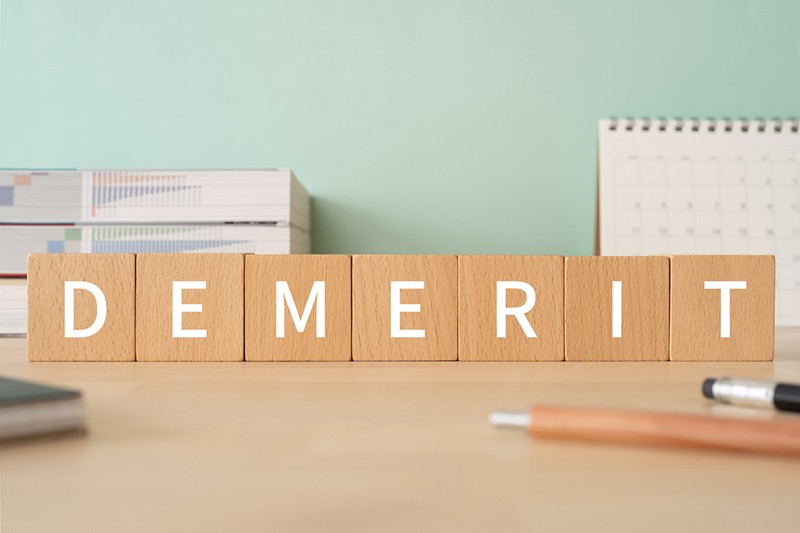
経営者や社長が現場に出ることには、いくつかのデメリットが存在します。
社員の主体性が失われ、優秀な人材が離職する
経営者が現場に過度に関与すると、社員は自分で判断する機会を失い、経営者に依存するようになります。
その結果、社員の主体性が損なわれ、とくに優秀な人材は自分の裁量権を求めて離職することがあります。
経営者の時間が制限され、経営業務が疎かになる
現場仕事に時間を割きすぎると、経営者は組織運営や経営に必要な重要な業務に十分な時間を割けなくなります。
これにより、会社全体の戦略や長期的な成長計画が後回しになり、経営の質が低下する恐れがあります。
経営者の業務過多で組織全体のパフォーマンスが低下する
経営者が現場を含むすべての業務を引き受けてしまうと、経営者自身の業務過多が原因となって、経営判断が遅れてしまうケースも。
その結果、組織全体のパフォーマンス低下につながる可能性があります。
管理職が育成されず、組織に悪影響を与える
経営者がすべての業務を管理すると、管理職が成長する機会が奪われます。
その結果、管理職が機能せず、組織の中で上司と部下の関係が希薄に。
この状況は、社員の成長を妨げ、組織の士気低下を招きます。
経営者本来の役割が果たせなくなる
経営者が現場で働きすぎると、本来の経営業務である意思決定や戦略立案に時間を割けなくなります。
また、新規事業の立ち上げなど、会社を大きくしていくことも後回しになりがちです。
もし取り組めても、現場に出ながらでは十分に成果が発揮できるかは微妙でしょう。
これにより、会社の未来を築くための重要な役割を果たせなくなり、会社の成長が停滞します。
経営者・社長が現場から離れて会社の成長のためにすべきこと
では、経営者や社長が現場から離れて会社の成長に専念するためには、どのようなことが必要になるのでしょうか。
経営者が現場から離れて経営に集中するためには、まず社員に仕事を信頼して任せることが不可欠です。
現場で直接作業しているのは、信頼して任せられないことが多いからです。
信頼できるスタッフを育成し、仕事を任せる環境を整えることが重要となるでしょう。
部下に仕事を任せるコツについては、下記コラムもあわせてご覧ください。
次に、経営に集中するためには、会社全体の方向性を示す明確なビジョンを掲げ、それを社員と共有することが求められます。
ビジョンが浸透していれば、社員は自発的にそのビジョンに基づいて動くことができ、社長が現場にいなくても成果を上げることが可能に。
また、社員が効果的に成果を出せるよう、マニュアルの整備や作業フローの明確化など、仕組みを整えることが必要です。
誰もが一定の成果を上げられるような環境を作り出せれば、社長は経営に専念でき、組織全体の効率も向上します。
そして、社長が現場から離れるためには、組織コーチングを活用し、社員が目標を達成できる力を養うことも重要です。
組織コーチングを通じて社員の主体性が高まると、社長が現場にいなくても、組織は自立的に動くことができるようになります。
ジョンソンホームズの事例から考える成長ステージに応じた思考・マネジメントの必要性
住宅会社であるジョンソンホームズの事例ですが、20棟台から、50棟、100棟台へ棟数を伸ばした時期、私が何をやっていたかについて少しお伝えしたいと思います。
北米輸入住宅を販売する営業マンだった私は2001年、マネージャーを任されました。
前年24棟、社員は8名でした。
プレイングマネージャー時代
当時のジョンソンホームズはすべてにおいて、グループ企業に依存した"お荷物会社"でした。
「ダメならジョンソンやめるかも」というところからスタートし、どうせダメなら自分たちの好きなようにやろうと決めました。
組織として「社員みんなで考える」ことを大事にし、この時期に社風の基礎が完成しました。
ブランドは輸入住宅「インターデコハウス」1本。
私自身11棟売り、30棟台に。
マーケッター時代
50〜60棟台になりました。
本を読みまくり、セミナーに出まくっていました。
チーム制を導入し、また、集客・育成・セールス・アフターに関する仕組みづくりに取り組みます。
この時期、セクショナリズムが起こり、社員はバラバラ。
一人ですべてを取り仕切っていた私はというと、充実感たっぷりでした。
しかし、儲かっていませんでした。
インテリア事業をスタートすることになったため、権限委譲を決めました。
ブランドプロデューサー時代
90〜100棟台になりました。
インテリア事業と連動する住宅ブランドや、自然素材の家「ナチュリエ」などが誕生。
ブランド構築の楽しさを味わいました。
各ブランドを一つの会社のように運営し始めたのがこの時期です。
100棟を超えてからいろいろとほころびが出始め、私一人ではコントロールできないことが増えていきました。
また、権限委譲、人材育成に失敗し、組織的大混乱を起こすことに。
さらに、リーマンショックの影響から初の赤字を出し、一から出直すことになりました。
鳴かず飛ばずだった当社が50棟までいったのは、マーケティング思考になったこと。
そして、100棟までいったのは、ブランディング思考になったりプロデューサーになったりと、私自身が意図的に自分の役割を変えてきたことが関係していると考えています。
赤字後、起こっていることのすべては自分のせいだと考え、さまざまな会社を見て学びました。
自分たちは何のために存在するのか、何を大切にするのか、どうひとつになるのか。
つくった「いつまでも続く、自分らしい幸せな暮らしを提供します。」というミッションは、「良い会社をつくる」ということとともに、決してぶらさないジョンソンホームズの経営目的となっています。
また、大きな転機となったのは、2009年の規格住宅「COZY」の導入です。
輸入住宅を手がけ、ゼロからプランを描いて作品のような家をつくり上げることに一生懸命だった当時の当社の価値観ではあり得ないブランドですが、利益率は高くなり、棟数も増え、大きな成長につながったのです。
ただし、付け加えると、100棟までは棟数が伸びているだけで、営業利益はほぼ残っていませんでした。
会社を良くするのは数を売ることだと、とらわれていたのです。
会社というのは、良くなった瞬間から違うものになっていきます。
ジョンソンホームズでは、大企業になろうとするフェーズにおいて、マネジメントや営業の型作り・仕組化を怠っていたことから、"ぬるさ"が営業組織を弱くし、売れる人・売れない人の差も大きく開いていました。
その後、ジョンソンホームズでは営業改革を行い、年間300棟規模で活動しています。
成長ステージに応じたマネジメントの必要性と、会社は"生き物"であるということを実感しています。
会社の規模と経営トップが認められる人の量は比例する
成長ステージによって経営トップに求められる役割は違うため、今までのやり方や考え方にとらわれていては、次のステージに行くことは難しいと思います。
消費活動がモノそのものよりコト(経験・体験)に価値が置かれる今の時代、例えばデザイン重視で作品のような家づくりにこだわっているなら、棟数を伸ばすことは容易ではないでしょう。
デザイン性に富んだ作品づくりにこだわる経営トップが「家とはこうあるべき」思考を手放すことは、いわばアイデンティティの8割を捨てるようなものです。
しかし、そこを手放さなければ、ステージチェンジは実現できないと考えます。
私もそうでした。
私はすべてにおいて自分は社員に勝っていると思っていましたが、成長を見せる部下・社員に対して、自分の力を見せつけたかっただけ。
自分がキレキレの主役であることに満足していた時代がありました(そのあと、主役は社員であるべきだと気づきました)。
ジョンソンホームズが成長できてきた歩みのなかで、自分が大事にしている価値観以外に大事なことは山ほどあることや、人を嫌わない・相手を認めるということが非常に重要であることがわかりました。
会社の規模は経営トップが認められる人の種類の量と比例する、というのは自分にとって大きな気づきとなりました。
もしかすると、経営トップ自身のエゴが会社の成長を妨げているかもしれません。
平坦な道はありませんが、それでも当社が順調といえる感じで成長できてきたのは、トップとして私が自分自身の意識と役割を変えてきたからだと思っています。
参考になれば幸いです。
経営者・社長が「現場に出ない」ことが会社の成長への第一歩
経営者が現場に出たくなる理由は、事業への熱意や完璧主義、現場の楽しさにあります。
また、経営者は、現場から離れることで利益低下や尊敬を失う不安も抱えることも、現場を離れたくないという思いにつながっています。
しかし、経営者が現場に出ることには、社員の主体性喪失や経営業務が疎かになること、パフォーマンス低下のリスクが伴います。
現場から離れるためには、信頼できる社員に仕事を任せ、会社のビジョンを共有し、作業フローを整備することが重要です。
組織コーチングを活用することで、社員の主体性を高め、経営に専念することもできます。
経営のヒントを知りたいという方は、ぜひ一度ジョンソンパートナーズへご相談ください。
ジョンソンパートナーズでは、自社直営店で培ったノウハウを基に、全国のフランチャイズ加盟店様へマーケティングに関するアドバイスも行なっております。
私たちは、住宅フランチャイズサービスを通して全国の工務店様の経営を支援いたします。







